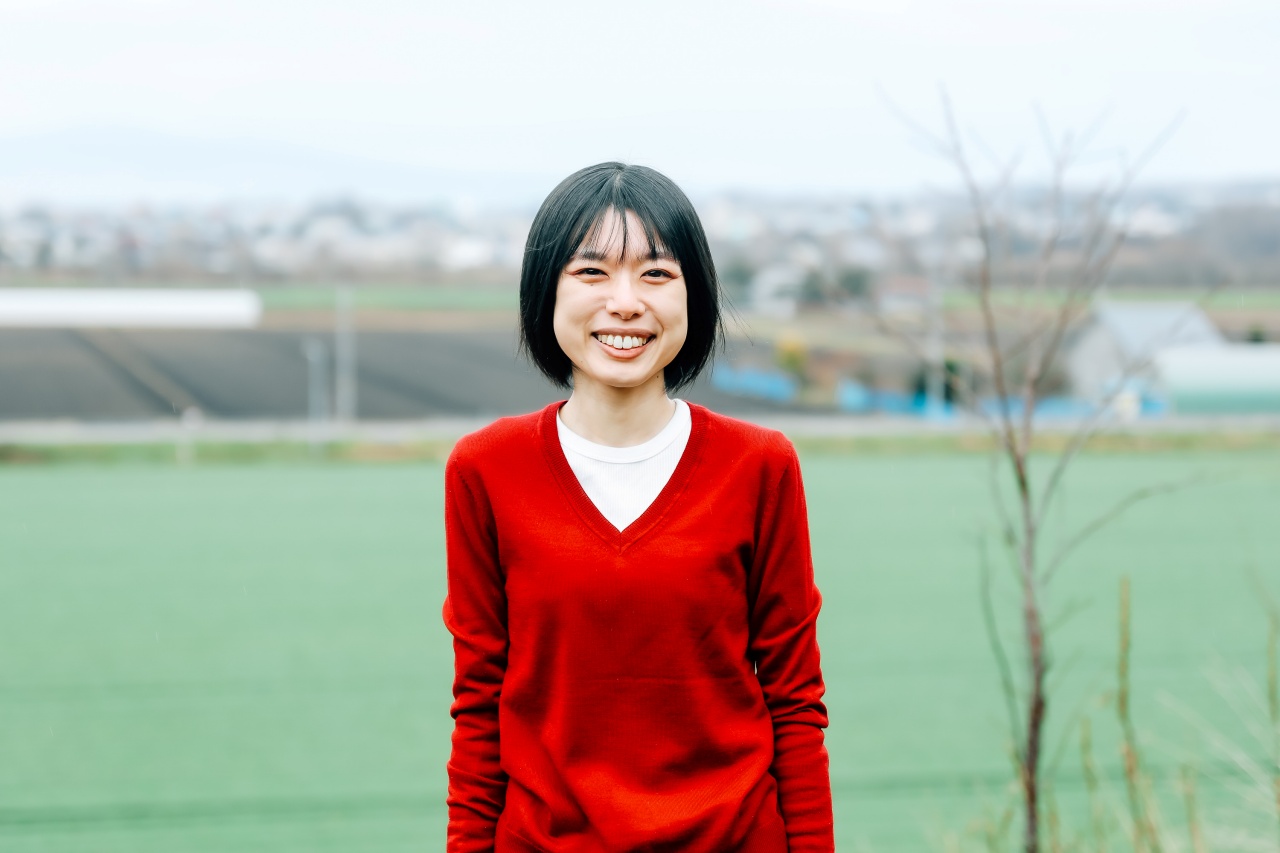【ドット道東ではたらく】徳島県から道東のローカルプレーヤーへ!小松輝<ボードメンバーインタビュー>
道東の未来をつくるコミュニティ「DOTO-NET」学生サポートスタッフの平塚真子です。
北海道の道東エリアを拠点に活動するドット道東は、2025年8月現在、フユコミット含め11名のボードメンバーで構成されています。
道東に関わる全ての人たちが、自分たちの理想を実現でき、住むと決めた場所で楽しく生きられる。
そんな未来を目指して活動していますが、
一体、ドット道東ってどんな人が働いているの?どんなお仕事をしているの?
こんな質問をいただくことが多くあります。
道東の他、東京や大阪を拠点にしているメンバーもおり、全員がフルリモート。二足以上のわらじを履いていたり、地元は道東ではない等々……経歴もさまざまです。
このボードメンバーインタビューでは、ドット道東で働くメンバーのことをもっと知ることができます。
今回インタビューするのは、ドット道東 理事の小松輝です。

小松輝/一般社団法人 ドット道東 理事
1994年、徳島県徳島市生まれ、梨農家の孫。徳島大学で中山間地域のまちづくりについて学んだ後に、浦幌町で地域おこし協力隊として働く。任期の3年間で観光事業の立ち上げに従事し、2019年に(株)リペリエンスを設立。旅行業を中心にツアー企画などに取り組んできた。2021年には浦幌町でハハハホステルをオープン。就業促進ポータルサイト「つつうらうら」を開設し、地域への人の流れを生み出している。
徳島県から、北海道・浦幌町へ
――現在は浦幌町で活動されている小松さんですが、出身は徳島県なんですよね?
小松 そう、生まれも育ちもずっと徳島県!大学までずっと徳島県だったんだ。
大学では、中山間地域の役割や田園都市計画的なことを学んでたよ。今の社会の中で都市計画として色々考えられていることを勉強したな。
研究室に配属されてからは、地域住民に地域の歴史を聞くオーラルヒストリーについて学んでいたよ。
そういうことをやってるうちに、いつの間にか「地域っていいな」って思うようになってたかも。
――大学での学びがきっかけで「地方」や「地域」に関心を持ち始めたのですか?
小松 元々は実家が梨農家だったこともあって、高校卒業するくらいには農家を継ごうって考えてたんだよね。だけど、両親には「農家なんて儲からない」とか「こんな仕事は辞めた方がいい」とかネガティブなことばかり言われてて・・・。
実際に、梨農家のある地区の周りがベッドタウンになっていくのを目の当たりにして、農業をやりたくない人がいるからなんだろうなとか、そこに価値を感じていない人たちが多いからなんだろうなと思ったのがなんとなくの問題視だったかな。
その時に農家に対してネガティブに捉えない社会を作っていかないと、第一次産業に携わっている人たちが誇りを持って暮らすことができないと感じたよ。だからそこを変えたいなと。
田舎で暮らすことがカッコ悪くないというか、都会と田舎で暮らすことの優劣はないという感覚を社会全体で作れたらいいなと思ったんだよね。

――小松さんは、大学卒業後に地域おこし協力隊として浦幌町に来られていますよね。なぜ浦幌町を選んだのでしょうか?
小松 1番の理由は、浦幌町に住む大人は子どもたちに町に帰ってきて欲しいと思っていること。だからこそ自分たちが町の良さを伝えたり、自分たちの営みの価値を伝えようとする姿勢に感動したからかな。
例えば、地域の大人がここで暮らす子どもたちを一緒に育てようということで、学校教育を通して農家民泊をやったりだとか、地域の活性化について中学生が考えて発表するだとか、こういったことを学校の先生だけではなくて、町の人が関わっていくという取り組みが浦幌町にはあるんだよね。
これを「うらほろスタイル」と呼んだりもするね。
――実際に地域おこし協力隊としては、どのような活動をしていたんですか?
小松 1年目は、イベントやお祭りのお手伝いをしながら、町の人たちと繋がりを作っていってたかな。廃校した校舎を使ったプロジェクトがあったからそれの立ち上げのお手伝いもやったりしてた!
2年目からは農水省の助成金を申請して、それを使用してツアーを企画したよ。バードウォッチングやハマナスの収獲体験ツアーとかね。
3年目は、会社を立ち上げて旅行業を始めたね。ツアーの予約管理やガイドをしたりしてたよ。その中で町に宿が必要だと思ったから、ゲストハウス(今のハハハホステル)を作る計画を立ててたな。

“定住する気ゼロ”だった僕が、浦幌に暮らし続けるワケ
――地域おこし協力隊の任期後も浦幌に住み続けている理由はありますか?
小松 正直なところ、地域おこし協力隊として働くことを決めた当初は、今後何をするのかも見えていない状態だったから定住しようとは全く思ってなかったんだよね。
でも、3年間活動していて、応援してくれる人がいたり、今後こうなったらいいなという形が見えてきてたから、それを自分がやるしかないなって思えたんだよね。
決め手はないけど、3年間でまだ何もできていないから応援してくれる人たちのもとでもう少し頑張ってみようって思ったんだ。
――移住して価値観の変化などはありましたか?
小松 空が広くて、風が気持ちよくて、まっすぐな道がどこまでも続く――そんな北海道の景色の中で暮らしていると、「ここ、なんか肌に合うな」って自然と思えてきたな。
それに、田舎にも沢山仕事があるから生きていく方法はいくらでもあるということに気づいたよ。一つの仕事で生きていける分稼がないといけないとかではないと思うし。だから失敗しても絶対死なないなと。
このことに気づいてから挑戦のハードルが下がった気がするよ。

――挑戦のハードルを下げれる!大事だなと思います。田舎の良さに気づかない人も多いのかなと私は思うのですが、小松さんはどう思いますか?
小松 そうだね。都会での暮らしを好むのか田舎の良さを知らないから住みたくないというのでは全然違うと思っている。
多分、大半の人がそうだと思うんだけど、田舎の良さを知らないんだったら知れる機会が少なかったんだと思うし、子供の頃に触れる環境がなかったんだと思う。子供の頃から自然に触れて育った人とかは北海道が好きだろうし、本州の人からしたら北海道は憧れ。
もちろん好きな場所や住みたい場所で暮らした方がいいと思うけど、絶対的に都会で暮らしたいというのがなければ田舎の良さを知るとか、どんな暮らしをしたいかとかが実現できるところに住んだらいいのになと思うな。
なかなか変化を望まない人も多いけど、北海道は変わることができる余地や余白が大きいと思うよ!
――これからの浦幌が「こうなったらいいな~」という展望はありますか?
小松 20〜30代の同年代がどんどん増えていったらいいなと思ってる。
そうなるように仕事を作れたら良いなとか、起業してくれる人が増えたら良いなと思っているから、それに向けて動いていきたいかな。
ドット道東との出会いは、とある町のゲストハウス
――ドット道東との出会いはどこだったんですか?
小松 ドット道東が設立される前から知っていたんだよね。というのも、僕自身ゲストハウス・ハハハホステルを始めようとしていた時期に、阿寒町のゲストハウスに色々お話を聞きに行っていて、ちょうどその時にドット道東の立ち上げをしてたんだ。

――偶然なんですね!
小松 そうそう。それで僕がゲストハウスを始める時に町民向けの説明会イベントをやったんだけど、それをドット道東のメンバーが手伝ってくれたんだよね。
だから存在は知っていて、拓郎さんも含めて旅行などに行ったときに、ドット道東に関わるメンバーがもう少しいたらいいのかなと側から見て感じたから、「何かできることがあれば手伝わせてください」と声をかけたことがきっかけだったりする。
その時の話をすると長くなるんだけどね(笑)
――ドット道東の理事として、現在はどのようなことをされていますか?
小松 僕自身浦幌で会社を立ち上げているということもあって、浦幌近郊のお仕事などは僕が関わっているかな。僕が行政や町の人との繋がりを持ってドット道東の仕事を提案できたらいいなと思ってるよ。
固定した役割はないので細かいこととか瞬発的に忙しくなる時とか、突発的に起こる仕事に対してフォローしたりとか一緒になったりという感じ。

――お仕事をする上で大切にされてることはありますか?
小松 僕がいないと何かができないとか進まないとか、決まらないとかそういうわけでは全くなくて。だけど、僕がいるから話が進みやすいっていうことは社内的にあるのかなって思ってる。
僕はドット道東のメンバーでもあるし、道東の一つの町で活動している1人でもあるから、両方の目線で話せるということは、ドット道東の中の役割として持っておきたいなというのはずっと思ってるかな。
――最後に、ドット道東を通して、チャレンジしてみたいことや叶えたいことはありますか?
小松 浦幌という場所からはみ出して、隣町や道東エリアに自分が貢献できることを広げていきたいなという想いはあって。僕は今、住んでいる浦幌という町での暮らしをより豊かに楽しくして未来に残していきたいと思っているんだけど。もう少しそのエリアを広げて道東それぞれの場所で暮らしている人や挑戦している人たちが、残していきたいものとか作っていきたい未来みたいなものに対して関わることがこれからやっていきたいことのひとつです。
仕事探検メディア「#道東ではたらく」では、求人の他にも、道東で開催したインターンのレポートや道東ヤングが執筆したコラム等、さまざまな記事を公開しています。ぜひご覧ください。